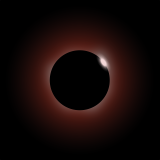どういう書き出しにするべきなのか、悩んで結局2週間が過ぎた。柄谷行人さん(以下、柄谷)には大学生の頃に『隠喩としての建築』で初めてお目にかかって以来、そのキャッチーなネーミングと独特の論調が頭から離れない。私が文学というものに影響を受けるきっかけとなった作品(芥川龍之介『藪の中』)に対し、柄谷は、「『藪の中』は我々に謎を提示するが、この謎のなかを生きるように強いはしない。「読者が作品に参加し構成しなおす」といった自由を与えない」と冒頭で言い放った。そういうわけで、「不条理の文学を先駆している」という見解を否認したのである。
読者がある作品のなかで漂うことができず、ただ作者芥川の「巧妙な手つきをみて興じる」しかないと論じられることは、私の文学に対する基本姿勢を揺るがすものであったかもしれない。作家は、昨日の世界には無かったものを、昨日までの世界にあった何かを使って、今日の世界に新たに存在せしめる役割を持っていると思われるが、そこに、たとえば柄谷のいう「手つきの巧妙さ」が入り込んだ場合には、読者が読書のなかで目指す「場所」のようなものから遠ざかってしまうのだろうか。
新たな知覚が個人のなかで誕生する瞬間には言葉にならない興奮がある。しかしそうした興奮が、あたかも様々な歪みや痛みの正体を解き明かすように振る舞いながら、実は現実の自分のそれに全く影響を与えることがない、というのは意外と少なくないのではないか。そうした時に何か不気味な存在を感じ取り、そうして興奮を覚えて過ごした時間の隙間で、何者かが無表情でこちらを見つめていたのではないかという漠とした不安が拭えなくなる。「高い買い物をしたのに、実際に使ってみれば、これがなかなか実用性のないものだった」あの感覚と似ている。外見こそ私を満たしてくれるであろうものが、時として毒となっている場合がある。その可能性を柄谷は示唆していたのではないだろうか。
芥川は『藪の中』を書いたが、彼はわれわれを閉じ込めている「藪の中」については何の示唆も与えていないのである。
柄谷行人『意味という病』「藪の中」p.231
観念がひとをくいつぶすことについて
『意味という病』のなかに「ものと観念」という章がある。本著の裏表紙に印字されている文とつながることだが、「在りもしないものが在るばかりでなく一切がそこからはじまる。ひとが観念をくいつぶすのではなく、観念がひとをくいつぶす」のだそうだ。柄谷は、自身に“戦後”という意識がないのは、“そこ”に生きていたからであると述べている。ほかに比較するものがないから、敗戦によって我々が何を得て、何を失ったのか、そんなことは私には分からないということなのだ。ここで柳田國男(以下、柳田)の「もの」と「観念」の話が登場する。柳田は、「明治初期に生まれた学者を支えていたのは孝行心だ」といい、次のように語っている。
人間には誰しも怠け心があり酒をのみに行きたい、女と遊びたいといふ気も必ずおこるのだが、そのとき眼頭にうかぶのが自分の学資をつむぎ出さうとする老いたる母の糸車で、それは現実的な、生きた「もの」である。ところが、私たち以後の人々は、儒教を知的には理解してゐても、もはやそれを心そのものとはしてゐない。
同上 p.289
柄谷は、「もの」の代替物である「観念」がひとびとを支配したが、一たび風が吹き荒れると吹き飛ばされてしまうような代物でしかなかった、と分析したのだ。「宙に浮いた観念がひとをつかむのは、すでにひとが宙に浮いた存在だから」だと続けている。「もの」をつかむことができず、その代替物として要請された「観念」だけがひとびとを支配している。このような状態は現在の社会、とくに都市部において実際に起きていることのように思える。
とはいっても、柄谷のいう「もの」とは単に事物のことを指すのではないようなのだ。もう少し「もの」についての理解を深めるために説明が必要である。
「もの」とは、事物ではなく、「言い表されれば観念になってしまうような「言葉」、すなわちわれわれの感受性にほかならないが、それは失われたときはじめて感じられる」としている。これは柄谷の経験から語っているものであり、戦後においてさえまだみようとすれば確かに「もの」があった、という個人的な体験のようにも聞こえる。「失われたときはじめて感じられる」というのが「もの」の正体だとしているが、その例として梅崎春生の『幻化』を取り上げる。
精神病院から抜け出した主人公は、「いろいろなものとのつながり」をもとめて、かつて兵隊として敗戦を迎えた坊津へやってくる。しかし他人とも風景とも「つながる」ことができない。私が忘れられないのは、主人公がチンドン屋の真似をしてひとりで砂浜を踊り歩く場面である。この光景はぞっとするほど陰惨であり、且つ哀切(あいせつ)である。
主人公が坊津へやってきたのは、いわば「もの」を見出そうとしてである。それができないで、彼はおそらく少年期にもっていた感覚を再現するチンドン屋の真似をして、かろうじて自己を「支へる」のだ。
同上 p.291
柄谷はこのあと、「『幻化』において梅崎が描いたのは、こういう「もの」あるいは「言葉」から絶たれて在る精神の風景である」と続けた。柄谷はこの作品を、自分自身の経験のように読まずにはいられない、とした。
個人的経験としての「もの」
少々傲慢な展開に感じる読者もいるかもしれないが、この柄谷の文章を読み、単なる批評というよりも、自分自身の経験として胸にこみ上げてくる何かを感じ取った者もいるのではないだろうか。実際、私は数ヶ月前に上に書かれたような、「つながり」をテーマにしたエッセイを書いている(『1,500kmの孤独』)。そこには故郷である名護市の玄関口「許田」の海辺に、やっとの思いでたどり着いた主人公が「なつかしいもの」をもとめて商店街「名護十字路」まで歩いてくる姿が描かれている。商店街に着いた主人公の目には、かつてみた風景ではなく、顔の見えない客の姿と親しみのない商品だけがみえる、というものだった。
自分で書いた作品の「書こうとしたもの」を探る、というのは非常に興味深い作業である。あの当時作品を書いた自分では分からなかったものが、実は上のような「つながり」をもとめた作品であったこと、そして作品中に登場する「タンナファクルー」や「はちゃぐみ」といった沖縄伝統菓子であったことは単なる偶然ではないように思えた。おそらく私にも「もの」が「失われた」ことが経験としてあったのではないだろうか。そういう気分で過去の作品をみてみると、たったの一度だけ書いたことのある短編小説『離別』のなかに「亡くなった祖父」を象徴する「ブーゲンビレア」が登場していることに気付く。やはりこれは単なる偶然ではない。私は自分がそうとは知らずに、「納得のいくもの」として書いていた作品のなかに、失われた「もの」を登場させ、「つながり」をもとめていた、そう解釈するのが今では一番自分自身を納得させるものとなってしまった。
そういうところでいくと、私は一貫して「同じこと」を書いてきたことになる。異なる風景を背景に置き、登場人物を変え、様々な着地をみせたが、結局のところ、私は「どこにも行けていなかった」のではないだろうか。というよりはむしろ、いろいろな場所に行くことで、「どこにも行きたくなかった」のではないだろうか。ほんとうは同じ場所に居続けたかったが、そうすることができない理由あるいは許せない何かがあって、その場所を離れざるを得なかった。こういう風に考えてみると、これは別に自分に限った話ではないように思える。人は色々な理由で故郷を離れることがあるし、色々な理由で故郷に残る。だから特別個人的な考えではないのかもしれない。
ひとが「もの」と「観念」の境界を上手く線引きできずに、ある記憶のなかを行ったり来たりすること、また「在りもしないもの」、つまり「観念」だけに支配され続けることを避けるためには、「もの」と「観念」を分けるための「経験」が必要なのかもしれない。それは柄谷がいうには「失われたときはじめて感じられる」ものである。私にとって「祖父の死」は「もの」の喪失を意味していたのだと、今になって気付いた。