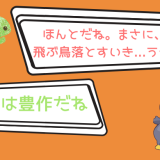旅するように本を読むことができるとしたら?
もしできたとしたら、それはとても素晴らしいことかもしれない。1ページめくるごとに、新しい土地の新しい空気が吸えて、色々な困難に出くわし、それを見事に克服していけるのだ。読み終えた後のあなたはとても充実した顔で、街行く人々に「ハロー」と声をかけて通り過ぎていく。そんな様子のあなたを見た人々は、はじめは憎らしく思っても、けっきょくハッピーな気持ちになってしまう。あなたが放つ「満たされたオーラ」が街行く人々に伝染していくのだ。とても素敵なことである。
あるいは、そんな夢のようなシチュエーションは、たとえ旅するように本が読めたとしても起こらないかもしれない。「街行く人々にハロー」だなんて、ハワイでもあるまいし、できっこない。そんな声が聞こえてきそうである。そもそも、そんな会話自体が「東京」には似合わないのかもしれない。誰かへの不満をささやき、明日の仕事量に頭を抱え、「自分の置かれた現状に納得がいかない」から、誰かにふと冷たい態度を取ってしまいたくなる。優しくできない理由は決まって「忙しいから」「疲れているから」。
ところで、わたしたちは「忙しさ」を理由にどこへ行くのだろうか。本当に「幸せ」がその先に待っているのだろうか。そんなことは誰にも分からないが、もし「まだ間に合う」のだとしたら、僕は「旅するように本を読む方法」を知っておきたいと思う。
この文章を読んで、僕が都会の暮らしに少し疲れを感じてきていることを察する方も多いと思う。僕は別に都会での暮らしや働き方を批判したいわけではなく、「生き方は選べるのかもしれない」と少し希望を持ったのだ。それは今すぐに実現できないけれど、こうして体験を文章にしてみることで、もう一度信じることができるかもしれないと、自分に言い聞かせようとしているのかもしれない。自分が書き、自分から離れた文章が、想像以上に影響力を持つものだと、改めて認識したいのかもしれない。
これからする香港での話は、僕が「誰かに文章を届けたい」と思うに至った、きっかけの話である。この体験がなければ、『僕らのコーヒー』や『少年と川』、『1,500kmの孤独』のようなエッセイは書けなかった。言葉にならないまま、誰の目に触れることもないまま、ずっと後悔と共に自分の外に出ていくことはなかったと思う。こうして文章が書けていること、それ自体に、本当に感謝している。あの時、勇気を出して、まわりの反対を押し切って香港に行った自分は正しかったと、あの時の自分を慰めてあげたい。
体験の重要性
今では昔ほど「世界」は遠いものではなく、時間とそれなりのお金を出せば、手の届くものとなってしまった。ドキュメンタリーや海外取材班が撮った過去の映像作品を見ると、そこには「過去」という宿命的な隔絶が横たわっている。僕は大学時代に「文化人類学」という学問を専攻していたので、講義や課題でいつもその「過去」と向き合う機会が多かった。学び始めた当時はそれほど過去の意味するものや、真偽が重要でないこともあり、好奇心の赴くまま学んでいたのを覚えている。けれども、大学2回生の春に決心した香港への1人旅をきっかけに、僕と過去の関係は、あるいは僕と文化人類学の関係は徐々によく分からないものとなってしまった。
体験がもたらすもの
体験がもたらすもの、それは失望かもしれない。
「香港のアバディーンという港町に、現在も海上生活者がいる」との情報を仕入れた当時の僕は、8日間の日程を組んだ。はじめの3日間は九龍半島とニューテリトリー、香港島の北側(コーズウェイベイ)をまわり、日帰りでマカオ、残りの日でアバディーンに滞在する予定だった。英語もまともに話せないから筆談用にメモ用紙を持ち歩いた。『深夜特急』のように言葉の通じない現地の人とも意思の疎通が図れると思ったのだ。
しかしいざ使う折になって、よく考えてみれば、スマホにグーグル翻訳が備わっていて、音声サポートも万端だから、一度もメモ用紙を取り出すことはなかった。他にも、初日の宿泊先―これはとても困った―というのが、あの「チョンキンマンション」だったのだ。
Booking.comで借りたその宿は、4棟の雑居ビルが複雑に絡み合った建物の8階部分にあり、そこにたどり着くには1階のインド人たちをかき分けて進み、1棟に1台しかない故障寸前のエレベーターに乗る必要があった。8階に上がってみて初めて、階段フロアが鉄格子で閉鎖されていることを知った。「火事が起きたらどうするのか」「エレベーターが故障したら飢え死にでもするのだろうか」そんなことを考えながら、眠れない夜を過ごしたのを覚えている。
孤独を味わうこと
生まれて初めて実行した1人旅である。しかも海外渡航2度目にして8日間だ。ごく控えめに言って孤独だった。一日に何度も腕時計を見たし、なるべく人のいる商業施設をあてもなく歩き回った。そうして2日目を過ごしていると、その日の夕方には日本に帰りたくなった。早くも味噌汁が飲みたくなった。
とはいえ、帰国まであと6日もある。「ここで宿にこもっているわけにはいかない」と思い、山頂や100万ドルの夜景を眺めるためにひたすら歩きまわった。分かったことは、酒でも飲めば気は紛れるし、移動を続けていればそのうち眠くなり、宿で目を覚ませば帰国の日へと近づくということだった。日本人とも会えず、YES・NOしか言えない状態の人間には、孤独な状況を開き直るしかなかったのかもしれない。
信じること
4日目の朝、僕はとても不思議な気分で目が覚めた。今すぐ香港島の南のアバディーンへ行って、海上生活者と写真でも撮ってみたい!と思ったのだ。朝の8時にチェックアウトを済ませ、ローカルバスに乗り、10時過ぎにはアバディーンの港近くの公園でハトに餌をやっていた。思いがけず、香港1人旅は本来の計画へと動き出した。
しかし着いてみると、港から見える海には1つも建物らしきものは見当たらない。それどころか、1人も海上生活者らしき人に遭遇しないのだ。しばらく途方に暮れていると、「南Y島行き」という看板が見え、波止場に小型船が停泊しているのが分かった。なんと往復300円だった。迷うことなく僕は船に乗り、Lamma Island に上陸した。そこで目にしたのは、海上に浮かぶ無数の建物であり、行政から特別に許可を受け海上に住む人々だった。
旅の副産物

ラマ島に着いて驚いたのはそれだけではなかった。港に着いてすぐ出迎えたのは50メートル程の屋台ストリートと、そこに長らく滞在しているらしい欧米人だった。店では低音の効いたヒップホップが流れ、昼間にも関わらずバーボンウイスキーを飲む人たちがいた。「観光地」というのが初めの印象である。しかしなぜこんな外れの島に人が集まるのだろう?海上生活者が珍しいだけでは人は滞在しないはずである。僕は島に2つある港のうち、発電所がある港の側から歩みを進めて、島の大部分を占める小高い山を登山者に続いて登っていった。
けっきょく2時間以上歩くことになったが、途中の低地には白い砂浜のビーチがあり、ちょっとした休憩所になっていた。登山者はここで荷物をおろし、水着に着替えて泳いだり、日光浴をするようだった。ある人は日陰で本を読み、ある人は観光案内所でもらった島内マップで現在地を確認していた。「なんだ、ちょっとしたバケーションに最適な島なのかもしれないな、宿もちらほらあるみたいだし」そう納得したのを覚えている。退屈な島かと思えば、とても活気にあふれた島だった。
「あっち」と「こっち」の淡いで
その日最後の船が出る時刻になって、僕は波止場の桟橋で佇んでいた。見渡す限り続く水平線と、凪の湾、徐々に点き出した建物の灯を見ながら、とても不思議な感情にとらわれていた。なぜだか分からないけれど、今にも泣いてしまいそうだった。特に大きな失敗はしていないし、ただ山道をひたすら1人で歩いただけなのに、この島を去るのが、とても名残惜しかった。
よく分からない感情をこらえながら桟橋を歩き、乗客が船を待つあたりに来て、僕はふと後ろを振り返った。その時、なにかよく分からないものが僕を突き抜けて通り過ぎていった。島から伸びるコンクリートの桟橋の途中が、くすんだ街灯の灯に照らされていた。島の山の向こう側から藍色の雲が静かに右から左へ流れていた。風はほとんど無く、微かに潮の香りがした。
僕はまたここに来るかもしれないし、来ることができないかもしれない。でもどちらにしても、そこで見た景色はもう二度と見ることができないものだと分かって、こらえていた感情がすーっと消えていくのが分かった。それ以来、僕はラマ島を訪れていない。
「辺境」を信じること
沢木耕太郎さんは『天涯』(シリーズ全6巻)にて、「旅の発端は夢であっても、旅先で目にするのものは現実である。しかし、旅先で目にするものが現実だったとしても、その旅を持続させるのは、やはり夢である」と書いた。
僕はこの文章が好きである。嘘が無く、とても正直で、かつ力強い。
わたしたちは簡単に旅行に出かけることができる。行きたいと思った場所に、時間とある程度のお金があれば、とりあえず行くことができる。それはとても素晴らしいことだと様々な旅は教えてくれる。やはり体験が必要だと思い知らされるのもこの時だ。
しかし同時に、旅に出れば出るほど、徐々に「夢」が失われ、「現実」が世界のすべてを占めていくような恐ろしさに直面するかもしれない。すべてが「現実」に変わってしまうこと―それは「夢」のもつ想像力が発揮されない世界を意味している。違う言い方をするならば、映画「Never Ending Story」の「nothing」が迫ってくるのを、わたしたちは阻止しなければならない。
そのためには、わたしたちが「辺境」を信じること、そしてそれは「すぐ近くにある」ということを忘れないことにあるのかもしれない。