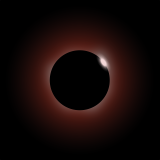まずは、簡潔に内容をまとめよう。この本で言っているのは、愛を求めながら、愛を得られなかったゴッホの、その引き裂かれた感情のすき間からあの絵が生まれたのだ、ということだ。
僕にとって大事な本になった、のか、大事な本になるだろう、なのかはわからないけど、とにかくそういうことを言ってもいいと思えるような、いい本だった。僕自身の人生経験と共鳴するからだとかいう理由ではなく、ゴッホという人間の面白さが伝わるからこその良さ。ゴッホの人生を哀れに思っても、別に自分に引く付けて読めるわけではない。僕には、ゴッホほどの激しい愛は備わっていない。いや、ちょっと不正確だ。僕には、ゴッホのように心の声を枯れつくしてしまうほどの、愛を欲望する激しさを持っていない。
彼は愛を求めすぎた。他人の愛を自分に向けようとするために発した心の声が枯れるほどに。愛を欲しているとは彼は言っていないだろう。しかし、手紙に、絵に、切り落とした耳に、その心の声は閉じ込められていた。果たしてその声に、彼が望んだ形で応えてくれる人はいなかった。
だからと言って、ゴッホの周りの人を責めることは決してできない。彼らは「普通」だったのだ。普通にゴッホを思い、彼らなりに普通にゴッホを愛していた。弟のテオは十分すぎるほどにゴッホの世話をした。ゴーギャンだって、1人でゴッホの元に来てくれたのだ。そこに愛がないとは言えない。それでも、ゴッホには足りなかった。なぜだろう、とおもう。ゴッホの愛への欲望は、どうしたら満たされたのだろうか。そもそも、どうしてゴッホの心はそれほどまでに愛への飢えを感じるようになってしまったのだろうか。
僕は思う。自然に湧いてくるこういった問は、そもそも問として正確ではない。ゴッホの絵を見て湧いてくる感情は、単なる哀れみではない。つまり、愛を求めながら、それを十分に得られずに死んでしまったゴッホへの哀れみではないのである。それではなんだというのか。僕は思う。それは、ゴッホが愛を知らなかったのだということへの哀れみである。彼が激しく欲望していたのは愛ではなかったのだ。いや、これは言い過ぎかもしれない。自分を棚に上げてしまっている。僕だって愛を知らないだろう。僕が言いたいのはつまり、ゴッホが求めていたのは、愛そのものであったのだが、そもそもそんなものは存在しないにもかからわず、(カントの言葉をもじって言えば)「愛自体」を人に求めていたのである。これは、愛を知らない、ということと等しいのではないか。存在しない、あるいは知り得ないものとしての「愛自体」を他人に求めていたのだ。だからこそ、満たされることなどありはしないのである。
高階秀爾は言う。ゴッホは自殺したのだと言われるが、それは違う、と。「彼ははっきりと『自殺』を決意していたわけではないし、むしろ何とかしてなお生きようと苦闘していた」。確かに結果的には自殺としか言えない死に方をした。間借りしていた店の主人からピストルを借りて、自らの腹を撃った。そして、それを聞いて駆け付けた弟テオの腕の中で命を落としたのだから。自分で自分を撃って、それが原因で死んだのだから、自殺である。
しかし、そう言っていいのだろうか。なぜ、彼は心臓や脳ではなく、腹部を撃ちぬいたのか。本当に死のうとする人間のやることではない。ゴッホの行為は高階が言うように、耳を切り落とす行為の延長線上にあるものだった。その先にあるのは「死」ではない。そうではなく、彼が求めてやまなかった「愛」であるはずだったのだ。自分を傷つけることで、誰かからの愛を得られるはずだったのだ。
37歳で没したゴッホがもっと長生きしていたら、と夢想する。彼は「愛自体」にたどり着けたのかもしれない。しかし、私たちに残されているのは、37歳までに描かれた絵だけである。彼の人生をこういっていいかもしれない。彼は愛に閉じ込められて生きてきた。しかし、閉じ込められているゴッホはそれが愛だとは知る由もない。外に愛があるのではないかと、その愛を夢想して絵を描き続けていたのだろう。愛を知ってる気になっている僕たちは、そんな彼の絵を見て、愛の輪郭を描けるかもしれない。