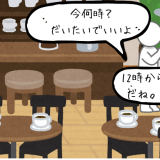もし「右」や「左」がなかったら―いったいどんなことが起こってしまうのだろうか。普段生活していて、そんなことは考えないと思う。けれども、よく晴れた午前に、書店の本棚の前で、このタイトルについてしばらく頭を悩ませていると、「もし→(右)や←(左)がなかったら」とか「もし↗や↙がなかったら」なんてことを段々と考え始めてしまったのである。そうすると、もうこの本を読まずにはいられなくなって、そして読んでみたら最後、僕の頭の中には「右」や「左」がない世界が拡がっていってしまったのだった。
豊かな北極
いきなりではあるが、本とは関係のない物語から紹介しよう。
ある日本の取材班が、およそ「未開の地」といわれていたアマゾンやユーラシア大陸の奥地に乗り込み、現地人と交流するテレビ企画が行われていた。だいたいの流れから行けば、現地人の暮らしぶりを取材し、そこにある「哲学」というか「宇宙観」のようなものをおよそ掴みつつ、テレビ企画としての一応のまとめに着地するはずである。
しかしある企画で、現地人の女性たちに、都会のファッションに身を包んでもらったり、都会の暮らしぶりを体験してもらって、その心境の変化を記録しよう、といった試みが行われた。結果はどうなったか、というところだが、ここがとても興味深い。
彼女らは「ここには何もない。わたしたちの故郷(日本語でいうところの「雪原」)こそ豊かである」と言葉を残したのだ。

なにをもって世界はそこに「ある」のか
わたしたち日本人の感覚であれば、「豊かさ」が意味するところは「モノの充足」や「便利さ」と結びついている。もう何年も前から「物に囲まれて生活する現代人は貧しい」とか「ミニマリズム」といった言葉が出回っているが、それでもやはりわたしたちは消費の在り方をあまり変えられていないし、物欲も尽きることがなければ、次から次へと「新しいもの」を欲しがってしまう。
何だかんだ言って、モノに囲まれることは、わたし(わたしたち)を満たしてくれる、ということなのだ。
そこで先ほどの彼女らの言葉に戻ってみる。では「雪原こそ豊かである」という言葉をどう理解するべきなのだろうか。答えは「豊かさ」の意味するものが、現代人とずれているところにある。
彼女らが取材班の前で言ったのは、雪原には生活に困らないだけの食料や娯楽などの選択肢が豊富にあり、日本にはまだ知られていない広大な地下世界が広がっているのだ、ということではない。
彼女らが取材班の前で言ったのは、雪原には(彼女らこそ知るところの)「意味」が充足していて、ここ(都会)には「意味」が足りない、ということだったのだ。
「意味」の意味

いろいろな言説を積み重ねた上で、一切の意味を否定することは文学批評などで読んだ試しがあるが、わたしたちの身近な生活のなかで「意味」が不足していると、いったいどうなってしまうのか、想像してみてほしい。都会に生きる人間がそれを実現するためには「砂漠」や「雪原」に行くのが手っ取り早いと思われる。
「砂漠」や「雪原」にはいったい何があるのだろうか。もちろん答えは「何もない」。「何もない」とはいったいどういった状況なのか、それが「意味」がない状況ということなのだ。
目の前に広がる景色や光景の一切が「わたし」と無意味であること。そういった時に、わたしたちには不思議な現象が起こる。それは「見えているのに、見えていない」という現象である。
なにをもって世界はそこに「ある」のか、あるいは、なにをもって世界はそこに「ある」ことができるのか、それは「意味」によって、また「言葉」によって「ある」ことができるのかもしれない。だから、いわゆる「未開の地」から出てきた彼女らにとって、都会には何もなかったのだ。
悔しいような気もするが、モノやイメージ(表象)にあふれている都会では、いったい何が「わたし」と「意味」で結びつくのか、正直よく分からない人も多いかもしれない。そんな時には、壮大な自然を目にし、そこに「わたし」と繋がる「意味」を発見してみてはどうだろうか。ちょうどシナイ山の頂上で、神からお告げを聞いたモーセのように。
イメージの絶対的貧困の砂漠において「わたし」を発見し、ただ「わたし」だけを愛しなさい
中沢新一『緑の資本論』
「右」も「左」もない言語
ちょっとした小話をはさんだところで、今回のトピックである。『もし「右」や「左」がなかったら』というのは仮説的なタイトルであるが、「右」も「左」もない言語なんて言われると、「そんな言語ほんとうにあるの?」という気がしてくるだろう。それくらい、日本語にとって「右」や「左」は重要な言葉なのだ。
もし「右」や「左」がなかったら?―それこそ「右も左も分からない」状況に陥ってしまうだろう。
ツェルタル語を話すテネハパ族の場合

メキシコのマヤ族の1つ、テネハパ族のツェルタル語には「右」や「左」という言葉が存在しない。ではどのようにしてコミュニケーションを取るのか、そこが本著において重要なウエイトを占めている。
日本人が「右」や「左」という言葉なくして「右も左も分からない」のは、日常生活におけるコミュニケーションに支障が出ることに他ならない。もしその問題が浮上した場合(なぜかは思いつかなかったけれど、明日から「右」や「左」がなくなると仮定して)、わたしたちはどのようにして対処することができるだろうか。
uphill と downhill
「右」や「左」のないツェルタル語では、物の場所や方向をあらわす時、「上り側(uphill)」「下り側(downhill)」に相当する言葉を使っていることが調査で分かっている。そしてそれは、「テネハパ村の立地条件そのものが空間表現に大きな影響を及ぼしている」のではないか、というものだった。なぜなら、彼らの住んでいる村が、海抜900mから2800mの起伏に富んだ地形に広がっていたからである。さらに平坦な地形がほとんどない、ということも調査から分かったのだ。
「上り側」「下り側」「横」の世界
そのような地形に住むテネハパ族にとって、わたしや彼といった「話者」が「右か左」にいることは特に重要ではなく、「上か下」のどちらにいるかが重要で、その距離がたとえ1㎝であっても1kmであっても関係なく、「上り側」「下り側」「横」の3つの表現で事足りることが分かった。
グウグ・イミディール族の場合
オーストラリア・ケープヨーク半島に住むグウグ・イミディール族の場合はどうだろうか。彼らにも「右」や「左」といった言葉が存在しないことが調査から分かっている。
「東西南北」の世界
テネハパ族が「上り側」「下り側」「横」の3つの表現で空間を切り取っていたことに対し、グウグ・イミディール族は「東西南北」で空間を切り取っていることが分かっている。ちょっとだけ例文を紹介したい。
- 「木の右側に立っている」の代わりに「木の北側に立っている」
- 「左に曲がって」の代わりに「北へ進んで」
- 「ちょっと詰めて」の代わりに「ちょっと東へ動いて」
いかがだろうか。これなら日常生活のコミュニケーションにさほど支障がないように感じる。この言語もやはり彼らが生活している環境に影響を受けており、生活の隅々まで「東西南北」の位置関係が影響していることが分かるだろう。さらに驚くのは、彼らの記憶の仕方で、ある物事が起きた時間を記憶していることはもちろんのこと、「方角」まで完全に記憶しているということであった。
サピア・ウォーフの仮説
「ことばが人間の考え方に影響を及ぼす」という問題を扱うとき、サピア・ウォーフの仮説は避けて通れないものになるだろう。この仮説には「言語によって、世界の見え方ないし切り取り方は違ってくる」という意味合いが込められている。詳しくは下記の記事からどうぞ。
もちろん『もし「右」や「左」がなかったら』という本には、このあとも沢山の調査報告が並び、人間がいかに多様であるか、また世界はいろんな「見え方」があるかが書かれている。有名な話ではあるが、虹が7色であるところを、5色であるとしたり、2色(「明るい色」「暗い色」)しかないとする言語が見られるなど本当に変化に富んでいる。興味のある方はぜひ『もし「右」や「左」がなかったら』を手にとって読んでみてほしい。
映画『メッセージ』を読み解くカギ

今回紹介したような「ことばが人間の考え方に影響を及ぼす」という問題を、文学作品に内包したのが『あなたの人生の物語』である。映画『メッセージ』の原作といわれ、著者はテッド・チャン、SF作家として世界的に有名な人物である。
言語が思考に与える影響というものを、サピア・ウォーフの仮説をもとに作品化したものとされている。未知の飛行物体が地球に接近し、その船体にいるタコのような生物と接触を図る物語だが、単なるSF作品と言ってしまうにはもったいない。
映画を見ていない方にはネタバレになってしまうが(映画レビューサイトではないのでご容赦いただきたい)、彼らが話す言語(ヘプタポッド:円形の言語)を習得した主人公には「未来予知」の特殊能力が備わってしまうのだ。
言語・思考・現実

サピア・ウォーフの仮説のうち、ベンジャミン・ウォーフが著した『言語・思考・現実』を読んだことがある。言語学に詳しい人であればスラスラと読める内容かもしれないが、かなりの時間をかけて読み終えたことを覚えている。おかげで印象に残ったストーリーもいくつかあり、映画『メッセージ』の「未来予知」の発想を支えたであろう話もあったので少し紹介したい。
「時制」のない言語
先ほどから「~ない」ばかりを使っていて申し訳ないが、ある言語(もう消滅してしまったかもしれない)についての調査で、「過去・未来・現在」といった時制が存在しない言語があることが分かった。
彼らの話す会話(ちなみに文字を持たない)は、すべて現在形で話されており、10年前に起こった隣村の火事と、昨晩のご近所で起きた夫婦喧嘩は「まるで昨日の出来事のように話されていた」との報告があったのだ。そしてそれは、およそ未来の出来事を話す時でも同じように話されていたというから驚きである。
つまり、「右」や「左」といった空間を切り取ることば以外にも、時制を切り取ることばさえ無い言語があるということなのだ。彼らには世界がどう見えているのか、世界はそこにどう「ある」のか、それは宗教を超えて、人間のもっと深いところに根差している「ことば」から多大な影響を受けているに違いない。
言語人類学から見える景色
「人類学は面白くなければ意味がない」と『タテ社会の人間関係』でお馴染みの中根千枝さんは言いました。それだけ多くの発見に富み、変化が感じられる学問だという意味だったのかもしれません。
今回紹介した『もし「右」や「左」がなかったら』という本は初版1998年のものなので、最新の研究結果からは少し遠のいたものとなっているかもしれませんが、人類学が何かを知らない読者にとっては、今日でもなお新しい発見に満ちているでしょう。
こうした「ことばと文化の関係」について研究している学問は、言語人類学といわれ、心理学の研究をベースとしていたり、認知科学の研究成果を理論武装したりと、柔軟性のある学問と言えるかもしれません。
「世界中のさまざまな文化に住む人間をどのように理解するべきなのか」という問題を「ことば」との関係の中から見出すこと、それは決して堅苦しいものではなく、映画『メッセージ』のような、ロマンチックでかつスピリチュアルな景色を見せてくれるものだと、少しは感じて頂けたのではないでしょうか。